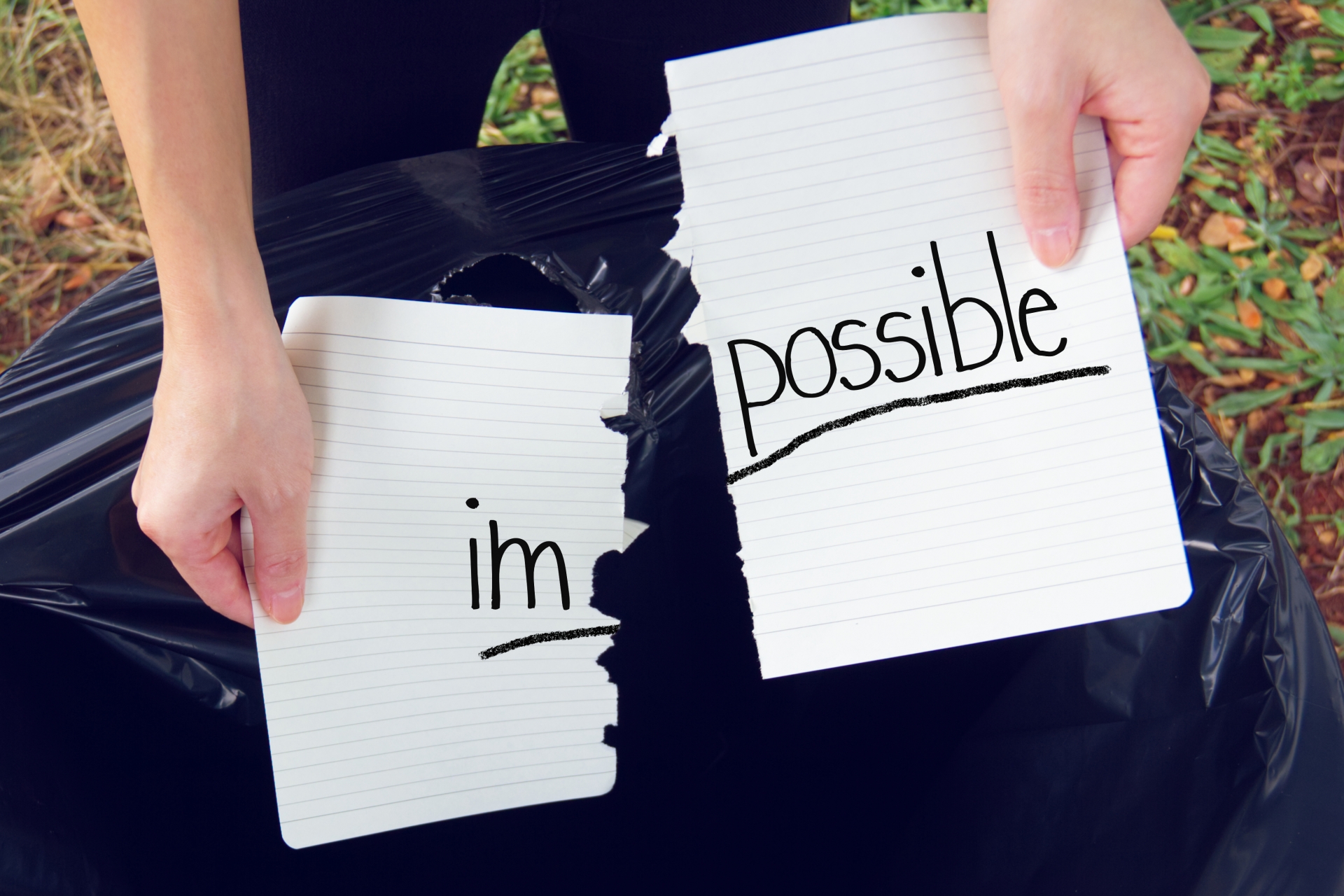成績が伸びない理由は「できる」だった
長年オンラインで指導をしていると成績が上がらないという相談を受けます。
そして、お母さんとの会話の中で実は原因が見つかることがあるのです。
目次
できるの意味
申し込みの前にいつも保護者の方と電話でやり取りを必ずします。
そして、私の塾は通常の指導は基礎からやるのですが、この話をするとこんなことを言われます
例えば

とか

と。最初はその話を鵜呑みにしていたのですが、途中から上がらない理由が分かってきました。
成績の上がらない子の家庭の特徴
指導していて成績が上がらない家庭は以下のポイントがありました。
・とにかく先に進みたがる次へ次へと言う
・難しい問題を解くと成績が上がると思っている
結局は
・身につけようということを優先しないで、やるということを優先していた
わけです。実際に伸びていない子はやっていないわけではなく、やっているのに伸びていないので結局は身についてないのです。
実際に指導してみた結果
実際に指導がスタートすると言われた通り簡単な問題はできます。
【主語】【述語】の問題を出すとできますが、やはりつまずきます。
さらに難しい問題をやると全くできません。お母さんが言っていた

というのは本当に初歩の初歩の問題ができるという意味だけなのです。
ですが、実際の問題を解く法は基礎の基礎だけではなく、本当に主語と述語がしっかりと頭の中に意識してできないと問題が解けないのです。
習い事で考えてみると
別な例で考えてみますとピアノピアノではドレミファを習いますよね。
そのときに順番にドレミの練習をしたときにまるで当たり前のように弾いています。
そのときに「ファ」と言われて

という風にやっているレベルでは当然ドレミファが弾けるいるとは言われませんよね。
できるというのは本当に当たり前のようにできるのができるということなのです。
算数の国でもそうです。算数の九九でも「いんいちがいち」「いんにがに」「いんさんがさん」と順番に問題を解いていって
いつでも
どこでも
どんなとき
でも九九は言るようになります。
そして、それができた時点で自分は九九ができると言るのです。
それが例えば

と言われて

なんて言ってやるとこれはできたうちに入りませんよね。だから本当にできるというのは空気をするぐらいできるようにならないといけないのです。
国語に戻って考えると
先ほどの主語と述語の問題でもそうです。例えば、こんな簡単な例をできます。問題はすべて
僕は太郎です。
彼は次郎です。
私は花子です。
こんな問題だとできます。ですが、さらにちょっとひねって
象は鼻が長い
とか
今日は天気が良い
とすると間違うことが増えてきます。さらに
君こそ主役だ
と変えるとつまずく子が増えてきます。
それで実際の入試でも出題された主語の問題です。
ふと見上げた窓の外に、庭の赤い鳥が赤い屋根の上に止まるのを見た。
この問題は最後の「見た」という単語の主語を答えなさいと言うものです。
実際には解答を間違う子が多いです。正解を言うとこれには主語がありません。
「見た」のは人か何者かなので、主語が省略された問題なのです。それを不正解にしてしまう子が多いわけです。
基礎が当たり前のようにできる
他にもあります。例えば、中学受験で言えば

と思って問題を解かせると「速さと時間と距離の関係」が怪しいのです。
ですが、本人に聞いてみると

と言います。実際に簡単な問題だとできます。ですが、ちょっと単位を変えたりすると途端にできなくなるわけです。
具体的な例で言うと
100km先の親戚の家まで行きます。時速50kmで行くと何時間かかりますか?
という問題。解答は単純に
100km÷50km=2時間
という計算になります。これは簡単になりますですが次はどうでしょうか?
100km先の親戚の家まで行くのに秒速20mで行くと何時間かかりますか?
これはそのままでは解けないです。これは秒速20mを時速に換算して計算しないといけません。
これは「秒速を時速に直す」というブロックと時間を求めるのに「距離を速さで割る」という2つのブロックができないと解けない問題だからです。
応用問題ではなく基礎の基礎から
実際にこういった問題がしっかりできて応用問題ができるようになりす。
まずは当たり前のことを空気のようにできるようにする必要があります。間違っても簡単にできたと思わないことです。