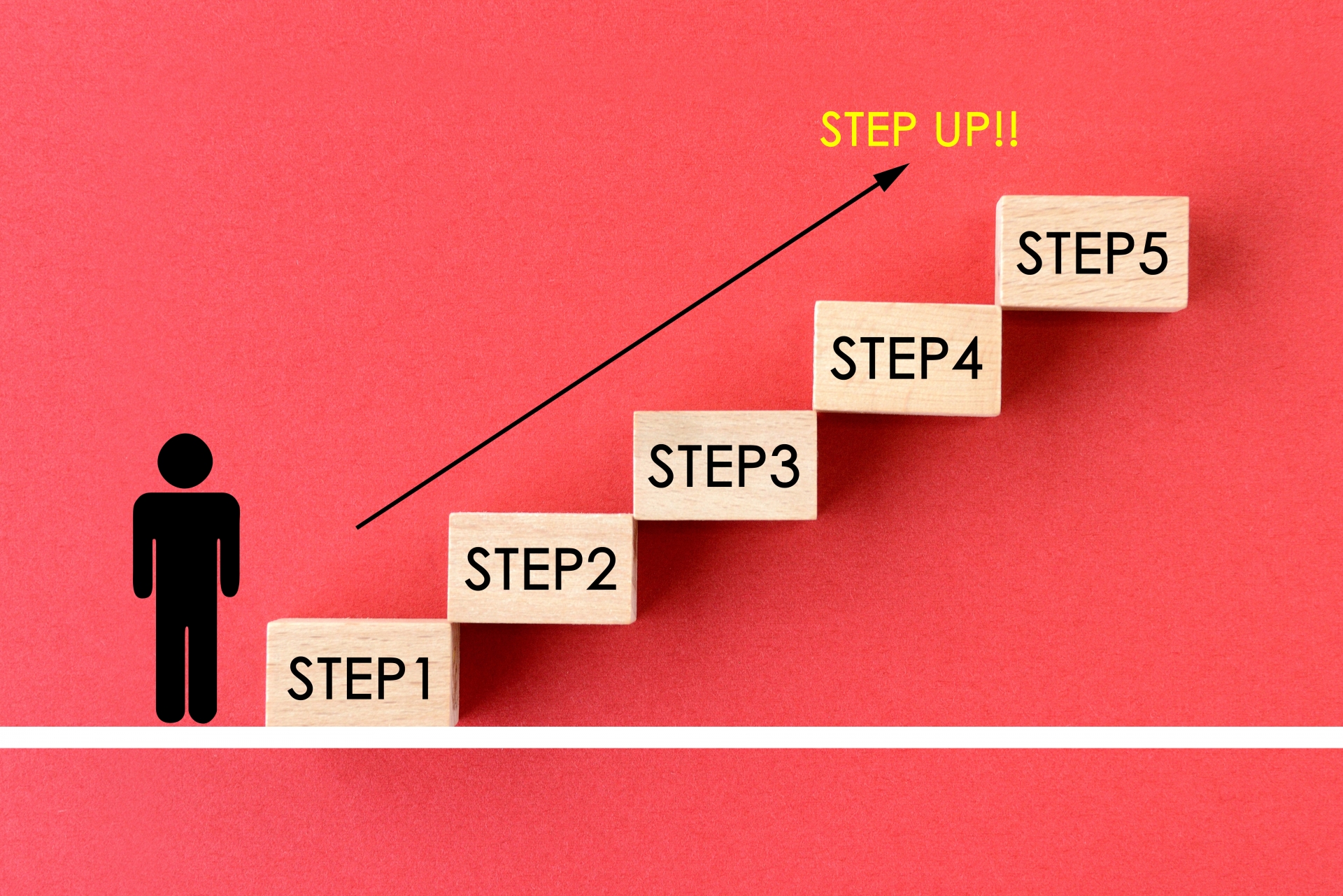ずっと電話面談が続いています。模擬試験の結果が出てきて悲喜こもごもです。
目次
できているけれどまずい
特にお子さんが長男や長女とい第一子の場合は親御さんも勝手がわからないので、親御さんが焦るかもしれません。
ただ指導していると
「できているけれどまずいな」
ということもわかっているので。その話をします。
正解でもダメな理由
小さいときから塾に通わせていると目先の結果に対して一喜一憂してしまうときがあります。
具体的にいうと
・正解であってホッとする
・不正解だとダメ
とか
・点数が良かったらOK
・点数が悪かったらNG
そんな感じです。実はこの中に色々な危険がはらんでいるのですその話をします。
実際に指導しているとは、点数か取れていても
「この子は将来が困るだろうな」
という子もいます。あるいはそのとき悪くても。
「後半伸びてきますよ」
いう子もいます。それがわかるのは
「問題を解くときの考え方、解き方のプロセス」
です。単純に「丸暗記」とか「パターンだけ」で覚えている子は成長が途途中で止まってしまいます。
ただ問題なのはそこでの親の対応です。親御さんが


と思っていると私が

と私がその話をしても多分、その忠告を聞かないと思います。過去に何度もやったことはありますが、事実を認められないのです。
いえ、多分自分の子育てを否定された気分になるのかもしれません。
あるいは、「目の前の結果がすべてだから」と思ってしまうからなのかもしれません。
何でもそうですが、うまくいっていても、その中にいくつもの危険がはらんでいることがあるのです。
極端な例で書きますと
100kmの道のりを時速100kmで走行して1時間で行けたとします。これは効率で行ったらいいですよね。
それを100kmの道のりを時速50km で行くと2時間かかってしまいます。
すると時速100 kmの人を参考にして、

何ていいませんよね。というのは時速100 kmで行くというのは交通事故を起こすリスクが高まるからです。
それだったら
「もう少しスピードを落として、時間がかかってもいいので安全に行って欲しい」
というのが本当です。もし時速100kmのスピードで移動して、事故をしてしまっては元も子もないからです。そういうことはわかりますよね。
世の中では、短期的に見えると「良い」と思うことが、長期的に見えるとマイナスになることがあるのです。
「浪人できて良かったね」
指導している子の中は大学受験に失敗して、浪人する子もいます。人にもよりますが、

という子もいます。そして、本人にも伝えます。

と思うかもしれませんが、もちろん、信頼関係ができている前提です。
というのは、高校受験が推薦で、勉強らしい、勉強をしてこなかった子は一度本当勉強する必要があるのです。
その浪人した子にもいっていましたが、

というくらいしたそうです。というのは、私もその子が自分の子であれば
「ここで痛い目に遭っておいた方がいいだろうな」
と思っていました。それで浪人して
「受験はそんなに甘くない」
と感じたり、
「勉強はこれだけやれば結果が出るんだ」
と理解してくれたりすればいいと思っていたからです。
正解でも注意すること
子どもが問題をどう解いているのかわかりません。というの頭の中がわからないからです。
ですが正解だとしても、どのように解いたのかを確認していくと見えないものが見えてきます。そこを注意しないとダメです。
指導していて途中で伸びなくなるかっていうのはこんなパターンが多いです。
・小学校のときはできた
・中学校のときにちょっと下がる
・高校に入ったらただの人
・大学にいったら全然できなくなる
・社会人になるとできた面影もない
すごくお金と時間をかけてきたのに結局こうなってしまった。
「なぜなの?」というふうに考えてしまうわけです。それは方向性だけです
プロセスを大事にする
論理エンジンを使用していても大切なことは
「どう解いたのか」
を質問して説明させることです。正解だからO というわけではなく、その途中経過が大切です。
たまたま答えがあったのか?それとも考えた上で間違ってしまったのか?
考えて間違った場合はそれを修正していけばよくなっていきます。
しかし、たまたまあった場合は逆に自分の力がつかなくなるので注意が必要です。