勉強しているのに成績が上がらない子の見直しです。
成績が上がらない子の見直し
成績が上がらないこと言う場合は1つ1つの確認が必要です。1回の授業が身についているのか
勉強しているのに成績が上がらない場合は1回1回の勉強が本当に身についているかチェックします。
具体的に言うと
・理解したのか説明させる
・確認のテスト
です。勉強したことが本当に身についてるのかは、まずは確認することです。
実際の指導でもそれをやっているだけなのです。「わかった」と言うのであれば「どういうことなのか?」という説明させます。
できた場合は必ず「確認テスト」を入れるということです。
そうすることによって毎回の勉強で結果が出ているのかがわかります。
テストをやっているが上がらない場合は
そして難点なのが毎回の確認テストはいいんだけれども、結果が出ない場合です。
その場合は
・勉強内容が腑に落ちていない
のです。別の言い方をすると
・イメージ化できていない
のです。国語でもそうですが、成績が上がってくるのときには途中で

というつぶやきがあります。その後に成績が上がってきます。
指導していてもその言葉が出たら基本的には指導が終わりです。
後は論理エンジンを使ってどんどんさせていけばいいからです。というのはそういう勉強に頭の中が切り替わったからです。
例えば、信号機の色を覚える場合です。「赤が止まれ」ですよね。
「赤は止まれ」と機械的に覚えるのも勉強です。ですが、

ということをもう1歩進んで調べてみるわけです。そうすると
「赤色波長の関係で遠くまで届く。だから、止まれを赤色にしています」
(大きく見える、血の色だから気をつけるなど説もあります)

と。そういう風なことがわかってくると「なるほど。そういうことなのか」ということで腑に落ちます。
理由がわかれば、覚えたら忘れにくいのです。ですが、単純に覚えるだけだと忘れやすいのです。
例えば、算数の「2×3=6」と「3x2=6」とすると答えは一緒です。
「6」だけを見るとどちらでも同じですが、どこが違うのかというのを具体的に考えるのです。
友達が、最初は3人遊びに来るので、1人ケーキを2個ずつ用意します。
後の方は友達が2人遊びにくるので、1人に3個あるケーキが2皿あるというように考えます。
そうするとトータルでは同じですが、意味が違ってくるというのがわかってきます。
そういう風に説明して理解させるわけです。
実際に生活に根差した考えだと、お遣いで

言われた場合は、状況によって異なります。
確かに、親がきちんと指示すればいいのですが、社会で使える子は
「誰が来るの?」
と質問して、その背景まで知ろうとするのです。
そして、相手がケーキを食べているところをイメージして買い物に出かけます。
友達が3人の場合は
「2種類のケーキを各3個」
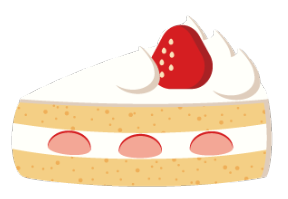
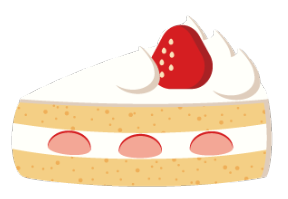
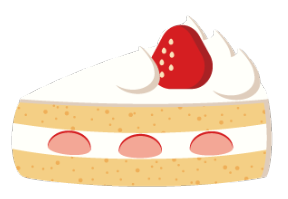
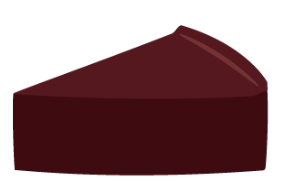
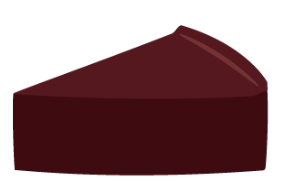
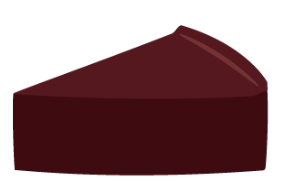
買ってきますし、2人の場合は
「3種類のケーキを各2個」
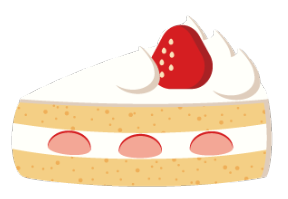
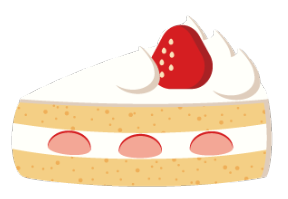
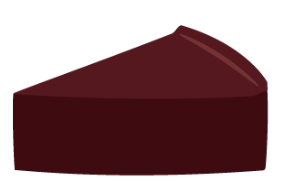
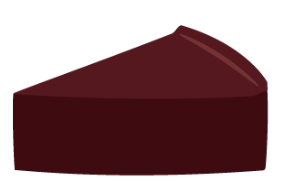


買ってくるようになります。これが生きた勉強です。同じケーキを6個買ってくることはないと思います。
あるいはバラバラに6個買ってくるのかもしれません。
丸暗記という勉強法では上滑りしているのでそういう風に腑に落ちたというものがないのです。
つまり、頭を使っていない勉強なので残りにくいのです。
それをチェックする方法は別のテストをする
そういった子には別のテストをします。普段、使っているテストではなく少し角度を変えた問題です。
それでテストをするわけです。同じパターンだと暗記しているのすると本質をわかっている子はそのテストでもできます。
ですが、理解できていない単純に覚えているだけの子はテストの問題が変わると解けないのでここで理解していないのがわかります。
ここがポイントです。
相談はこちらです。
